目次
EGRとは何?
EGR(Exhaust Gas Recirculation/排気再循環)とは、エンジンから出た排気ガスの一部を再び吸気側に戻す仕組みを指します。このシステムは主に、燃焼時の温度を下げ、NOx(窒素酸化物)の発生量を減らすために使用されます。EGRバルブが開くことで、排気ガスの一部が吸気マニホールドへ再循環し、空気中の酸素濃度を下げることで燃焼温度を低下させます。
1960年代以降、アメリカを中心に環境規制が強化され、日本でもトラックや乗用車にEGRシステムが採用されるようになりました。現在では、ディーゼル車だけでなくガソリンエンジン車にも導入されています。EGRは、環境負荷低減と燃費改善の両立を目指す近年のエンジン技術における基本的な要素です。
トラックにおけるEGR導入のメリット・デメリット
EGRをトラックに導入することで、排出ガス性能の向上と燃焼効率の最適化が期待されます。一方で、構造上の課題やメンテナンス性の低下といったデメリットも存在します。
メリット
EGRの最大のメリットは、有害なNOx排出を効果的に抑制できる点です。排気ガスの一部を再循環させることで吸気中の酸素濃度が低下し、燃焼温度が下がります。その結果、燃焼過程で発生するNOxが減少します。特に大型ディーゼルトラックでは、EGRを用いることで排ガス規制に対応しながら、燃料噴射量や点火時期の最適制御を行うことが可能です。
さらに、EGRによって燃焼温度の上昇が抑えられるため、ピストンやシリンダーなどの熱負荷も軽減されます。これにより、エンジン寿命の延長や部品の耐久性向上にも寄与します。また、後処理装置(DPFやSCR)との併用で、環境性能を一層高めることができます。
デメリット
一方で、EGRにはデメリットもあります。再循環される排気ガスには微粒子(スス)や油分が含まれており、吸気側の汚れやEGRバルブの閉塞を引き起こすことがあります。このため、長期使用によって吸気経路が詰まりやすくなり、アイドリング不調や出力低下を招くリスクがあります。
また、EGR作動中は吸気に新鮮な空気が減るため、エンジン出力がわずかに低下する傾向もあります。特にターボ付きディーゼルエンジンでは、EGR制御が複雑化し、制御バルブや冷却装置(EGRクーラー)の故障リスクも増加します。これらの問題を防ぐには、定期的な清掃や部品交換など、メンテナンスを欠かさないことが重要です。
EGRシステムの仕組み
EGRシステムは、排気側と吸気側をつなぐ配管経路に設置され、バルブや冷却器によってガス流量を制御します。エンジンの種類によってその構造や動作原理が異なり、主に「ガソリンエンジン」と「ディーゼルエンジン」で仕組みが異なります。
ガソリンエンジンの場合の動作・仕組み
ガソリンエンジンのEGRは、スロットルバルブとEGRバルブの協調制御によって動作します。エンジン負荷が低い時にはEGRバルブが開き、排気ガスの一部が吸気側へ戻されます。吸気ガスに排気を混合することで燃焼温度が下がり、NOx発生を抑制します。
EGRバルブの開閉は電子制御式(ソレノイド式)が主流で、エンジン回転数や負荷、冷却水温などの条件に応じてECUがバルブ開度を細かく調整します。これにより、エンジン性能と排出ガス規制の両立を実現しています。冷間時や高負荷運転時にはEGRを停止し、燃焼安定性を確保する制御が行われます。
一部のガソリン車ではEGR冷却装置(EGRクーラー)が追加されており、再循環する排気を冷却してより多くのガスを吸気側へ戻すことができます。これにより、燃焼温度をさらに低下させ、NOx削減効果を高めています。
ディーゼルエンジンの場合の動作・仕組み
ディーゼルエンジンのEGRは、ガソリンエンジンとは異なり、スロットルバルブを持たないため、排気側の圧力と吸気側の差圧を利用してガスを再循環させます。EGRバルブは排気マニホールドと吸気マニホールドの間に配置され、必要なタイミングで開閉し、一定量の排気を吸気に戻します。
特にトラックなどの大型ディーゼルでは、EGRバルブとEGRクーラーを組み合わせて使用します。高温の排気をEGRクーラーで冷却し、吸気温度の上昇を防ぐことで燃焼効率を保ちながらNOx排出を抑制します。このプロセスにより、DPF(ディーゼル微粒子捕集フィルター)やSCR(尿素SCRシステム)などの後処理装置との協調制御も容易になります。
EGR制御はエンジンECUが担い、エンジン回転数・アクセル開度・冷却水温・排気温度などのセンサー情報を基に、EGRバルブの開度を最適化します。加速時や高負荷時にはEGRを一時的に停止し、最大出力を確保する一方で、巡航時やアイドリング時にはEGRを多く作動させ、燃焼温度を抑える仕組みです。
EGRクーラーの性能も、ディーゼル車におけるNOx低減効果を左右する重要な要素です。近年のトラックでは、水冷式EGRクーラーが採用され、冷却効率を高めるためにアルミ製フィンや多段構造を持たせています。これにより、熱交換効率を向上させつつ、燃費性能を維持したまま排ガス規制をクリアしています。
EGRの構造
EGRシステムは、エンジンの種類や排気量に応じて構成が異なりますが、基本的には「EGRバルブ」「EGRパイプ」「EGRクーラー」などで構成されています。構造的には大きく「内部EGR」と「外部EGR」に分類され、それぞれの方式によって制御方法や効果が異なります。
内部EGR
内部EGRは、排気バルブの開閉タイミングを制御することで、排気ガスの一部を燃焼室内に残す方式です。新しい吸気行程で一部の排気が燃焼室に残留し、再燃焼することによってNOxを低減します。機構的にはバルブタイミング制御(可変バルブタイミング:VVT)が活用され、追加の配管を必要としません。
この方式は主にガソリンエンジンに採用されており、構造がシンプルでメンテナンス性に優れています。また、外部配管を使わないため冷却装置が不要で、コスト面でもメリットがあります。しかし、制御精度が低いと再循環量が一定にならず、燃焼効率や排気特性にばらつきが生じることがあります。
外部EGR
外部EGRは、排気マニホールドから吸気マニホールドに配管を設け、バルブで排気ガスを再循環させる方式です。ディーゼルエンジンや大型トラックでは主流の方式で、EGRバルブやEGRクーラーなど専用部品によって流量や温度を精密に制御します。
冷却機構を備えた外部EGRでは、EGRクーラーで排気ガスを冷却することで、より多くのガスを吸気に戻すことができます。その結果、燃焼温度がさらに低下し、NOx排出を効果的に抑制できます。一方で、ススやオイルミストの堆積により配管やバルブが詰まりやすくなるため、定期的な点検や清掃が欠かせません。
※この動画は YouTube「株式会社アーネストチャンネル」様の公開動画を参考として表示しています。
トラックのことなら「シグマインターナショナル」
シグマインターナショナルでは、中古トラックの販売・買取だけでなく、EGRバルブやDPFなど排気系パーツの整備にも対応しています。EGR関連の不具合や燃費低下などでお困りの際は、ぜひ専門スタッフまでご相談ください。
まとめ
EGR(排気再循環)は、エンジンの排気ガスを再利用して燃焼温度を下げることで、NOxの発生を抑える重要なシステムです。ガソリン・ディーゼル双方のエンジンで採用され、環境負荷低減や燃費向上に貢献しています。
一方で、EGRバルブやEGRクーラーの汚れ・詰まりによる不調も多く報告されており、定期メンテナンスが不可欠です。EGRを正しく理解し、適切に管理することで、トラックの性能と環境性能を両立させることができます。



 0120-66-1742
0120-66-1742


 2025.11.26
2025.11.26



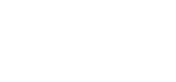 まずはお気軽に無料査定をどうぞ!
まずはお気軽に無料査定をどうぞ! 平ボディ
平ボディ  ダンプ
ダンプ  クレーン車
クレーン車  積載車
積載車  タンク車
タンク車  ミキサー車
ミキサー車  高所作業車
高所作業車  トラクターヘッド
トラクターヘッド  アルミウイング
アルミウイング  アルミバン
アルミバン  冷蔵・冷凍車
冷蔵・冷凍車  アームロール
アームロール  パッカー車
パッカー車  マイクロバス
マイクロバス  重機
重機  いすゞ
いすゞ 日野自動車
日野自動車 三菱ふそう
三菱ふそう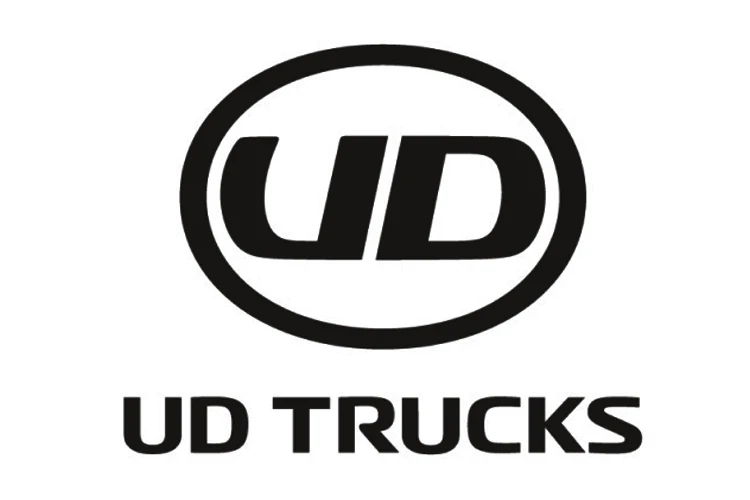 UDトラックス
UDトラックス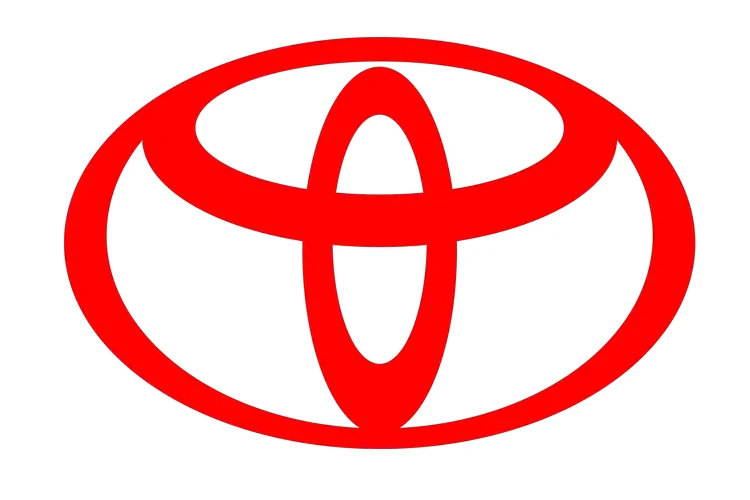 トヨタ自動車
トヨタ自動車 日産自動車
日産自動車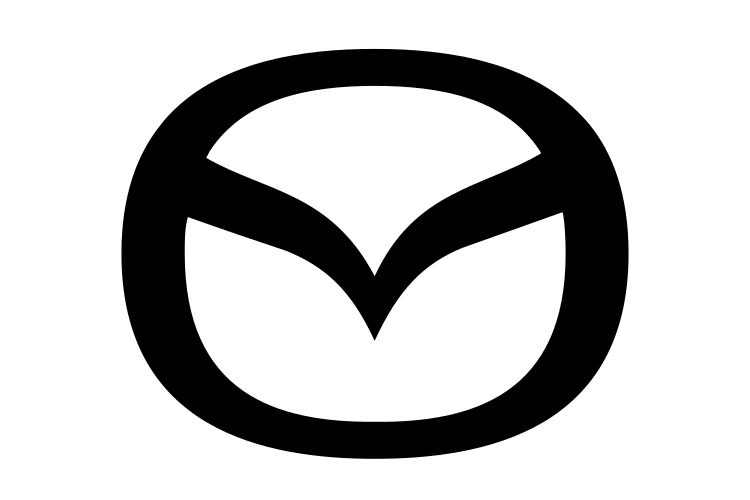 マツダ
マツダ